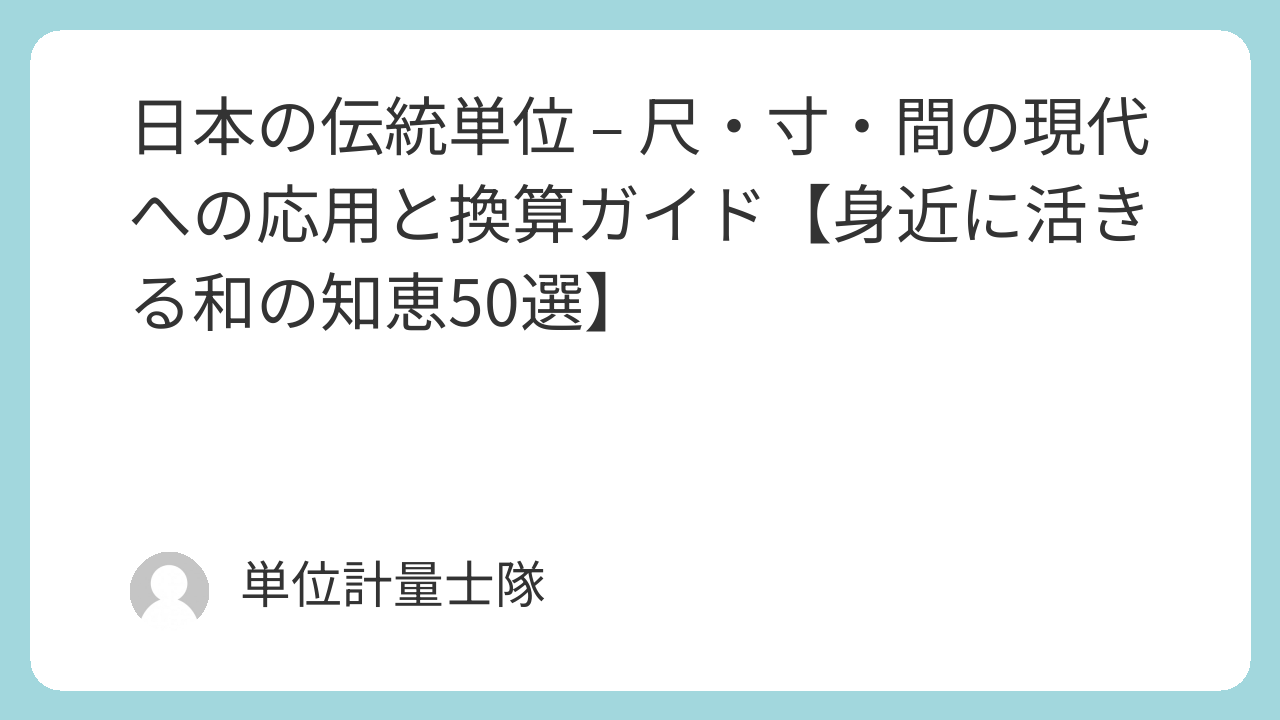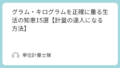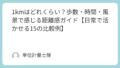日本の伝統的な単位「尺」「寸」「間」は、現代社会でもしばしば目にする単位です。
畳の大きさや着物のサイズ、建築の世界では今なお使われているこれらの単位。
でも実際のところ、1尺は何センチなのか、1間はどれくらいの長さなのか、感覚的に掴めている方は少ないのではないでしょうか?
この記事では、日本の伝統単位の基本から、現代の生活での活用法、メートル法との換算方法まで、わかりやすく解説します。
日本文化や伝統工芸に興味がある方はもちろん、リフォームや和室の設計を考えている方にも役立つ情報が満載です。
この記事でわかること
- 尺・寸・間の正確な長さとその成り立ち
- 現代生活での活用シーン50例
- メートル法への簡単な換算方法
- 日本建築や伝統工芸における単位の知識
それでは、日本の伝統単位の世界へご案内します。
日本の伝統単位の基本

日本の伝統単位は、人間の体を基準に発展してきました。
尺は成人男性の前腕の長さ、寸は親指の幅が由来とされています。
長い歴史の中で微妙に変化してきた単位ですが、現代では以下の換算値が一般的です。
尺の基本
- 1尺 = 約30.3cm(メートル法施行後は1尺=10/33m≒30.303…cmと定義)
- 基本的な長さの単位で、和服や畳、建築などで今も使用される
- 一般的に大人の腕の長さ(肘から指先まで)に近い
- 呼吸をしながら一歩進む距離とも言われる
寸の基本
- 1寸 = 約3.03cm(1尺の10分の1)
- 親指の幅に相当するとされる
- 細かい工芸品や道具のサイズによく使われる
- 料理の「一寸」も、この長さが語源
間(ま)の基本
- 1間 = 6尺 ≒ 約182cm
- 建築の基本単位として広く使われる
- 畳一枚の長辺の長さに相当
- 大人が両手を広げた長さに近い
その他の関連単位
- 分(ぶ):1寸の10分の1(約3mm)
- 厘(りん):1分の10分の1(約0.3mm)
- 里(り):36町(約3.9km)
- 町(ちょう):60間(約109m)
【実践テクニック】
- 自分の前腕の長さを測り、個人的な「1尺」の目安にする
- 親指の第一関節の幅を測定し、自分の「1寸」を知る
- 両腕を広げた長さを測って、自分の「1間」の感覚をつかむ
身近な物で感じる尺・寸・間

抽象的な数値だけでは実感が湧きにくいものです。
ここでは、身の回りにある物で尺・寸・間の感覚をつかむための例を紹介します。
1尺(約30.3cm)に相当するもの
- 一般的な定規の長さ(30cm)とほぼ同じ
- A4用紙の短辺(21cm)と長辺(29.7cm)の間
- 中型のタブレット画面のサイズに近い
- 大人の足のサイズ(かかとからつま先まで)
- 学校の教科書を3冊重ねた高さ
1寸(約3.03cm)に相当するもの
- 500円玉の直径(26.5mm)より少し大きい
- 一般的な消しゴムの幅
- ティースプーンの柄の長さ
- サイコロ一辺の2倍弱
- 親指の第一関節の幅
1間(約182cm)に相当するもの
- 一般的な大人の身長より少し高い
- シングルベッドの長さ(約195cm)より少し短い
- 冷蔵庫の高さに近い
- フルサイズの傘を広げた直径
- 一般的な玄関ドアの高さ(180cm)とほぼ同じ
【活用のコツ】
- 自宅の日用品で「物差し代わり」になるものを見つけておく
- スマートフォンの長さや幅も覚えておくと、急な時の測定に便利
- 自分の体の一部(指幅や歩幅など)と伝統単位の関係を知っておく
日本建築と伝統単位
日本の伝統建築は、尺・寸・間の単位体系を基本に設計されています。現代の建築にも息づくこの知恵を見ていきましょう。
畳と尺寸法
- 標準的な畳は1畳 = 1間×0.5間(約182cm×91cm)
- 本来は「六尺三寸四方」が基準だったが、地域によって微妙に異なる
- 京間:6.3尺×3.15尺(約191cm×95.5cm)
- 江戸間:6.0尺×3.0尺(約182cm×91cm)
- 中京間:6.15尺×3.075尺(約186.5cm×93.2cm)
柱間と建築モジュール
- 柱と柱の間隔は基本的に1間(6尺)
- 基本単位をさらに分割した「半間」(3尺)も多用される
- 「4.5畳」「6畳」「8畳」など、畳数で部屋の広さを表現
- 縁側の幅は通常2尺(約60.6cm)前後
天井高と開口部
- 伝統的な天井高は1間+αが一般的
- 障子や襖は通常7尺(約212cm)の高さ
- 戸の一般的な幅は3尺(約91cm)
- 神社の鳥居の高さも尺寸法で決められている
日本庭園と尺寸法
- 飛び石の間隔は1.5〜2尺(約45〜60cm)が歩きやすい
- 石灯籠の高さは通常4〜5尺(約120〜150cm)
- 茶室の躙口(にじりぐち)は2尺×2尺(約60.6cm×60.6cm)程度
【実践テクニック】
- リフォームの際は、尺単位の寸法を考慮すると和の雰囲気が出る
- 畳の種類を知っておくと、家具選びの参考になる
- 和室設計では「四方転び」(部屋の四隅に柱を配置する形式)を意識する
伝統工芸と尺寸法
日本の伝統工芸品も、尺寸法を基本に作られています。
美しい調和の秘密は、この単位体系にあります。
着物と寸法
- 着物の反物:幅1尺3寸(約39.4cm)、長さ12〜13m
- 帯の長さ:約4.3m(男性用は約3.6m)
- 袖丈:大振袖で約1間(約182cm)
- 身丈:身長に合わせて調整、約1.5間(約273cm)前後
茶道具と寸法
- 茶碗:直径4寸(約12.1cm)前後
- 茶筅:長さ約1尺(約30.3cm)
- 茶杓:長さ7寸(約21.2cm)程度
- 茶室の床の間:幅6尺(約182cm)、奥行き3尺(約91cm)が基本
刀剣と尺寸法
- 日本刀の刃渡り:2尺3寸(約70cm)が標準的な太刀
- 脇差:1尺5寸(約45cm)前後
- 短刀:1尺(約30cm)以下
- 柄(つか)の長さ:約8寸(約24cm)
和楽器の寸法
- 三味線の棹の長さ:約2尺4寸(約73cm)
- 琴の全長:約6尺(約182cm)
- 尺八:長さ1尺8寸(約54.5cm)が標準
- 太鼓の胴直径:用途によって様々だが、約2尺(約60cm)が多い
【活用のコツ】
- 工芸品購入時は尺寸法を理解していると、適切なサイズ選びができる
- 茶道や華道を学ぶ際に寸法感覚があると上達が早い
- 伝統芸能の衣裳や道具の選定にも役立つ
現代生活における尺・寸・間の活用法

伝統単位は過去のものではなく、現代生活でも活用できます。
日常のさまざまなシーンで役立つ知識を紹介します。
インテリアと空間設計
- 天井高:現代の住宅では8尺(約242cm)が標準的
- ベッドの高さ:1尺5寸(約45cm)前後が使いやすい
- ダイニングテーブルの高さ:2尺5寸(約76cm)前後
- ソファの座面高:1尺3寸(約39cm)程度
- 窓の高さ:床から6尺(約182cm)が視界良好
DIYと日曜大工
- 棚板の奥行き:1尺(約30cm)が標準
- 書棚の棚板間隔:1尺(約30cm)が本に適している
- 階段の蹴上げ:6寸(約18cm)前後
- 階段の踏面:1尺(約30cm)前後
- 手すりの高さ:2尺8寸(約85cm)が使いやすい
園芸と庭仕事
- 庭木の間隔:低木なら3尺(約91cm)、高木なら6尺(約182cm)以上
- 花壇の幅:奥行き2尺(約60cm)が作業しやすい
- 散水ホースの長さ:10間(約18m)あれば一般的な庭をカバー
- 植木鉢の口径:4寸鉢(約12cm)、6寸鉢(約18cm)などと表記
- 生け垣の高さ:5尺(約151.5cm)程度が防犯上も良い
料理と食事
- まな板の標準サイズ:1尺×1.5尺(約30cm×45cm)
- 包丁の刃渡り:菜切り包丁で6寸(約18cm)前後
- 鍋の直径:8寸(約24cm)が家庭用の標準
- 一口サイズ:1寸角(約3cm角)が食べやすい
- 寿司ネタの厚さ:3分(約9mm)程度が理想的
【実践テクニック】
- 家具購入時、「8尺(242cm)天井に合う」などのチェックができる
- DIYでは寸と尺の感覚があると、バランスの良い設計ができる
- 料理の切り方も尺寸の知識があると、見栄えが良くなる
簡単換算ガイド
伝統単位とメートル法の換算は、少し慣れが必要です。ここでは簡単な換算方法と覚え方を紹介します。
基本換算表
- 1尺 = 約30.3cm(正確には30.303…cm)
- 1寸 = 約3.03cm(1尺の10分の1)
- 1分 = 約3mm(1寸の10分の1)
- 1間 = 約182cm(6尺)
簡易換算法
- 尺からcmへ:数値を3倍すると概算値が出る(1尺→約30cm)
- 寸からcmへ:数値を3倍(5寸→約15cm)
- cmから尺へ:数値を3で割る(60cm→約2尺)
- cmから寸へ:数値を3で割り、10倍する(3cm→約1寸)
面積の換算
- 1坪 = 2間×1間 = 約3.3m²
- 6畳間 = 3間×2間 = 約9.9m²
- 1畳 = 約1.65m²(江戸間基準)
- 畳数からm²へ:畳数×1.65が概算値
建築でよく使う換算
- 1.5尺 = 約45.5cm(窓枠幅)
- 2尺 = 約60.6cm(縁側幅)
- 3尺 = 約91cm(廊下幅)
- 4尺 = 約121.2cm(和室押入幅)
【活用のコツ】
- 「3倍」の簡易換算を覚えておくと、現場で素早く計算できる
- スマートフォンのメモアプリに換算表を保存しておく
- 特によく使う寸法(3尺、6尺など)の換算値は暗記しておくと便利
単位感覚を養う5つの方法

尺・寸・間の感覚を身につけると、日本文化の理解が深まるだけでなく、実生活でも役立ちます。
効果的な5つの練習方法を紹介します。
比較記憶法
- 自分の体を物差しにする(指幅、手のひらの大きさ、肘から指先までの長さなど)
- 日用品のサイズを覚える(スマートフォン、クレジットカード、A4用紙など)
- これらと尺・寸・間を関連付けて記憶する
実物測定演習
- 和室や畳の実寸を測ってみる
- 伝統工芸品や道具のサイズを実際に測定する
- 尺貫法の物差し(曲尺:かねじゃく)を使ってみる
目測トレーニング
- 物の長さを尺・寸で予想してから実測する
- 畳の枚数から部屋の広さを予想する
- 歩数と間の関係を体感する(3歩で約1間など)
創作活動への応用
- 和風の庭や部屋を尺寸法で設計してみる
- 書道や折り紙で尺寸法を意識する
- 和裁や木工など伝統的な作品づくりに挑戦する
日常的な意識付け
- 買い物時に商品サイズを尺寸で考えてみる
- 身の回りの道具を整理する際に尺寸を意識する
- 日本の伝統芸能や文化に触れる機会を増やす
【実践テクニック】
- 尺のイメージ:大人の前腕、A4用紙の長辺より少し長い
- 寸のイメージ:親指の幅、500円玉より少し大きい
- 間のイメージ:大人の身長くらい、ベッドの長さに近い
まとめ
日本の伝統単位「尺・寸・間」は、単なる数値ではなく、日本人の美意識や生活様式に深く根ざした智恵の結晶です。
- 尺(約30.3cm)・寸(約3.03cm)・間(約182cm)の基本単位を覚える
- 身近な物で単位の感覚をつかむ
- 日本建築や伝統工芸に息づく尺寸法の美しさを理解する
- 現代生活でも活用できる場面は多い
- 簡単な換算方法(基本は3倍)を覚える
- 5つの方法で単位感覚を養う
日本の伝統単位を知ることで、和室のリフォームや伝統工芸品の選び方、さらには日本文化全般への理解が深まります。
ぜひ、日常生活の中で尺・寸・間の感覚を意識してみてください。
また、他の日本の伝統単位についても興味がありましたら、「貫(かん)と匁(もんめ)の基本」や「坪と畳の関係性」についての記事もご覧ください。
日本の伝統文化に息づく計り方の知恵を、現代に活かしていきましょう。
関連記事
- 1尺はどれくらい?身近な例でわかる伝統単位ガイド
- メートル法と尺貫法の変換ガイド
- 畳の種類と選び方 – 京間・中京間・江戸間の違い
- 和室のリフォーム基礎知識 – 伝統と現代の融合
- インテリア配置の黄金ルール – 空間を最大限に活かす寸法感覚