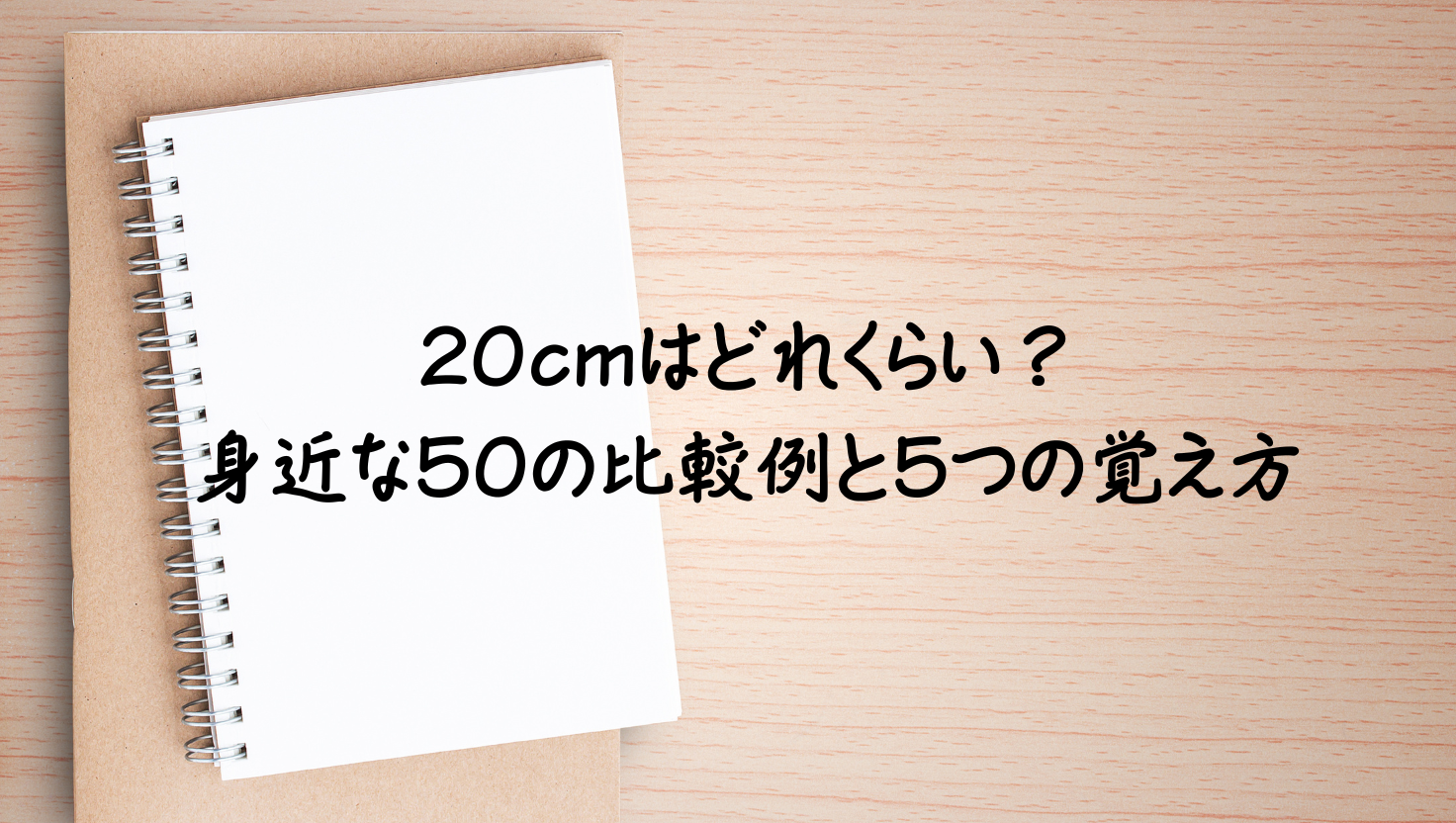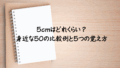20cmという長さは、日常生活のさまざまな場面で目にする身近な単位です。
しかし、実際に「20cm」と聞いたとき、具体的にどのくらいの長さなのかイメージできますか?
本記事では、身の回りのものを例に挙げながら20cmの感覚を養い、暮らしの中で役立つ「20cmの目安」を分かりやすく解説します。
測り方のコツから覚え方まで、この記事を読めば20cmの長さが直感的に分かるようになります。
五感で感じる20cm

普段の生活の中で、20cmの長さは様々な形で私たちの五感に触れています。
視覚や触覚を通じて、20cmの感覚を養うことができます。
触覚編
- 両手を広げた親指と人差し指の最大距離:多くの大人が両手の親指と人差し指を精一杯広げたときの距離がおよそ20cmになります。
- スマートフォン2台分の長さ:一般的なスマートフォン(約10cm)を2台並べるとほぼ20cmになります。手の平に収まる身近な電子機器で感覚を掴みやすいでしょう。
- A5サイズのノートの長辺:A5サイズのノートは約21cm×14.8cmなので、長い方の辺がほぼ20cmです。デスクに置いてあるノートで手軽に確認できます。
視覚編
- 500mlのペットボトルの高さ:一般的な500mlのペットボトルの高さは約20cmです。冷蔵庫や机の上にあるペットボトルで簡単に確認できます。
- テレビリモコンの長さ:多くのテレビリモコンは約20cm前後の長さです。毎日使うものなので覚えやすい目安となります。
- 標準的な定規の長さ:学校や事務所でよく使われる定規は15cmや30cmが一般的ですが、そのちょうど中間が20cmです。
聴覚編
- ギターの6フレット分:ギターのフレット間の距離は上の方に行くほど短くなりますが、1〜6フレット目までの距離がおよそ20cmです。
- ピアノの白鍵7つ分:ピアノの白鍵約7つ分がおよそ20cmです。音楽に親しんでいる人には分かりやすい比較かもしれません。
- CDケース2枚分:標準的なCDケースは約14cm四方なので、その長辺1.5枚分程度が20cmになります。
【実践テクニック:触覚で20cmをマスター】
- 親指と人差し指を最大に広げた状態を日常的に確認する癖をつける
- 定規で正確に20cmを測った後、その感覚を手や指で覚える練習をする
- 両方の手のひらを向かい合わせて、20cmの間隔を空けて置く練習をする
身近なモノで測る20cm

生活空間の中には、20cmの長さを持つ物や、組み合わせると20cmになる物がたくさんあります。
これらを知ることで、測定道具がなくても長さを推測できるようになります。
台所編
- 菜箸の長さ:一般的な菜箸は約20〜23cmです。先端から持ち手の付け根までが約20cmであることが多いです。
- キッチンペーパーの幅:多くのキッチンペーパーの幅はおよそ20cm程度です。料理中に手軽に確認できる目安となります。
- まな板の厚み10枚分:家庭用のプラスチックまな板は約2cmの厚みがあるものが多いので、10枚重ねるとちょうど20cmになります。
- 牛乳パック2本分の高さ:1リットルの牛乳パックの高さは約20cm前後です。冷蔵庫に常備している家庭も多いでしょう。
文房具編
- クリアファイル2枚を重ねた幅:標準的なA4クリアファイルの幅は約22cmなので、少し短めですがほぼ20cmと考えられます。
- ボールペン1.5本分:一般的なボールペンの長さは約14cmなので、1.5本分が約21cmとなり、ほぼ20cmです。
- 付箋10パック分の高さ:標準的な付箋1パックの厚みは約2cmなので、10パック重ねると20cmになります。
- B5サイズの横幅:B5サイズの紙は約18cm×25cmなので、短い方の辺がほぼ20cmに近いです。
生活雑貨編
- ティッシュボックスの横幅:一般的なティッシュボックスの幅は約23cmですが、短い側は約12cmなので、短辺の約1.7倍が20cmとなります。
- カセットテープ5個分の横幅:標準的なカセットテープの幅は約10cmなので、2個並べると20cmになります。
- 標準的なマグカップ2個分の高さ:マグカップの高さは約9〜10cmのものが多いので、2個重ねると約20cmになります。
【活用のコツ:キッチンで20cmを見つける】
- 菜箸やキッチンペーパーを使って、食材や調理器具のサイズを素早く確認
- 料理本に書かれた「〇〇を20cmの長さに切る」などの指示を正確に再現
- 保存容器のサイズ感を20cmを基準に覚えておくと収納が効率的に
自然界と20cm

自然界にも20cmという長さを持つ生物や現象がたくさん存在します。
季節や場所によって変わることもありますが、おおよその目安として覚えておくと便利です。
植物界
- バナナの平均的な長さ:食用のバナナは品種にもよりますが、平均的に約20cmの長さがあります。
- トウモロコシの穂の長さ:一般的な食用トウモロコシの穂の長さは約20〜25cmです。スーパーで見かけるとよい目安になります。
- ヒマワリの花の直径:栽培種のヒマワリの花の直径は品種によって異なりますが、約15〜25cmのものが多く、平均すると約20cmです。
- シダ植物の葉の長さ:室内観葉植物として人気のシダ植物の葉は、成長すると約20cm前後になるものが多いです。
動物界
- 金魚の最大サイズ:一般的な金魚は適切な環境で飼育すると、尾ひれを含めて約20cmほどまで成長することがあります。
- ハムスターのケージの標準的な幅:ハムスター用の小型ケージは約20cm×30cm程度のサイズが一般的です。
- 成猫の座高:くつろいでいる姿勢の猫の背中からお尻までの長さは、約20cm前後のことが多いです。
- カブトムシのオスの全長:日本のカブトムシのオスは、角を含めた全長が約20cmに達することがあります。
気象現象編
- 一般的な積雪量(大雪警報基準):多くの地域で大雪警報が出る基準となる積雪量は20cmです。
- 雨量20mm時の水たまりの深さ:道路の窪みなどに溜まる水たまりの深さは、降水量20mmでおよそ2cmになりますが、周囲10cm四方から水が集まると約20cmの深さになります。
【実践テクニック:自然観察で20cmを覚える】
- 散歩やハイキングの際、身近な植物の葉や花の大きさを20cmと比較する
- 家庭菜園で野菜の成長を20cm単位で記録してみる
- 自然の中での20cmの感覚を磨くことで、測定道具なしでも大きさを推測できるようになる
人体と20cm

私たちの体には20cmに近い部位がいくつもあります。
自分の体を測定基準として使えば、いつでもどこでも20cmを測ることができます。
指先の基準
- 成人男性の手のひらを広げた親指〜小指間の距離:手を精一杯広げたときの親指の先から小指の先までの距離は、平均的な成人男性でおよそ20cmです。
- 両手のこぶしを並べた幅:成人の握りこぶしの幅は平均約7〜10cmなので、両手のこぶしを並べるとおよそ20cmになります。
顔の部分編
- 成人の顔の縦の長さ:髪の生え際からあごの先までの距離は、平均的な成人でおよそ20cmです。
- 頭の周囲の1/3:一般的な成人の頭囲は約55〜60cmなので、その約1/3が20cmに相当します。
- 耳から耳までの頭部の幅:左右の耳の付け根を結んだ頭部の幅は、多くの成人でおよそ20cmです。
成長の20cm
- 新生児の平均身長:生まれたばかりの赤ちゃんの平均身長は約50cmですが、その約40%が20cmに相当します。
- 5歳児の成長量:子どもは5歳までに約20cm程度の身長が伸びる期間があります。
- 中学生〜高校生の3年間の平均成長量:思春期に入った中高生は、3年間でおよそ20cm程度身長が伸びることがあります。
【活用のコツ:自分の体で20cmを測る】
- 自分の手の広がりや指の長さを正確に測っておき、いつでも使えるようにする
- 服の袖や裾の長さを調整するときに、自分の体の20cmマークを活用する
- 子どもの成長記録を取るときに、20cmの目盛りを意識すると変化が分かりやすい
20cmの科学と歴史

20cmという単位は、科学の世界でも重要な意味を持ち、歴史的にも様々な文脈で使われてきました。
その背景を知ることで、20cmへの理解がさらに深まります。
単位としての20cm
- 2デシメートル:メートル法では、20cmは2デシメートル(2dm)と表現されます。
- 約7.9インチ:インチ単位では、20cmは約7.9インチに相当します。
- 約0.66フィート:フィート単位では、20cmは約0.66フィートです。
- 約0.22ヤード:ヤード単位では、20cmは約0.22ヤードに相当します。
精密科学の世界
- 電波の波長:UHFテレビ放送波の波長はおよそ20〜80cmの範囲にあります。
- 標準的な実験用ビーカーの高さ:化学実験でよく使われる1000mlビーカーの高さは約20cmです。
- 顕微鏡の標準的な作動距離:光学顕微鏡の接眼レンズから試料までの距離は、約20cm前後に設定されていることが多いです。
歴史的な20cm
- 古代の尺度「尺」:日本の伝統的な長さの単位「尺」は約30cmですが、その2/3が約20cmに相当します。
- ナポレオン時代の「フランス尺」:フランス革命後に一時使われた「尺」は約20cmでした。
- 古代ローマの「パルムス・マヨール」:古代ローマで使われていた長さの単位で、約20cm程度でした。
【実践テクニック:単位変換で20cmを理解する】
- 日常的に使う単位と20cmの関係を覚える(例:20cm = 約8インチ)
- 異なる文化や時代の長さの単位を20cmと比較してみる
- 科学や工学の分野で使われる20cmの例を調べてみる
20cmを覚える5つの方法

20cmの長さを直感的に理解し、日常生活で活用するための効果的な5つの記憶術を紹介します。
比較記憶法
- 常に持ち歩くものと関連付ける:スマートフォンやキーケースなど、いつも持ち歩くアイテムの長さを測り、20cmとの関係を覚えます。例えば「スマホ2台分」「キーケース3個分」など。
- 部屋の中の固定物と関連付ける:家の中に20cmちょうどのものを見つけ、それを基準にします。例えば「本棚の仕切りの間隔」「テレビ台の高さ」など。
【実践方法】
- 日常生活で目にするものを「20cmコレクション」として記録する
- 20cmのものを3つ以上覚え、どこにいても思い出せるようにする
指標作成法
自分の体を使って20cmを測れるように、体の部位の正確な長さを知っておきます。
【実践方法】
- 手の平や指の関節など、自分の体で20cmに近い部分を見つける
- 「親指から中指までの距離の2倍」など、組み合わせて20cmになる測り方を考える
- 定期的に定規で確認し、感覚を修正する
視覚化技術
20cmの長さを視覚的にイメージできるようにトレーニングします。
【実践方法】
- 20cmの線を紙に描き、それを何度も見て記憶する
- 目を閉じて20cmの長さをイメージし、実際の長さと比較する
- 異なる状況(縦、横、斜めなど)で20cmをイメージする練習をする
実践トレーニング
日常的に20cmを意識して使う機会を増やします。
【実践方法】
- 料理の際に、食材を20cm長さに切る練習をする
- DIYや裁縫で、20cmを測る必要がある作業を意識的に行う
- 「20cmチャレンジ」として、定規なしで20cmを描き、後で測って確認する
環境設定法
生活環境に20cmの目印を設置します。
【実践方法】
- デスクや冷蔵庫に20cmの線を引いたマグネットやステッカーを貼る
- スマートフォンの壁紙に20cmのものの写真を設定する
- 20cmを表す物差しやメジャーを常に目につく場所に置く
【活用のコツ:20cmの感覚をマスターする】
- 日常生活で見かけるものの長さを「約20cm」と推測する練習を繰り返す
- 複数の記憶法を組み合わせて使い、様々な状況で20cmを思い出せるようにする
- 1週間に1度は「20cmチェック」の日を設け、感覚が正しいか確認する
生活シーン別20cm活用術

20cmという長さは、様々な日常生活のシーンで意外と重要な役割を果たしています。
場面別の活用方法を見てみましょう。
料理とキッチン
料理の世界では、20cmというサイズは食材の調理や盛り付けに大いに関係してきます。
【活用術】
- 麺類を茹でるときの長さ:うどんやパスタを約20cmの長さに折ると、一般的な鍋で調理しやすくなります
- 野菜の切り方:大根やきゅうりなどを20cm間隔で切ると、煮物や漬物に適したサイズになります
- 巻き寿司の長さ:一般的な巻き寿司は約20cmの長さで切り分けると、6〜8切れに均等に分けやすくなります
DIYと修繕
家の修繕やDIYでは、20cmという単位がしばしば登場します。
【活用術】
- 棚の間隔:本や小物を置く棚の間隔を20cmにすると、様々なサイズのアイテムが収納しやすくなります
- 壁の下地:日本の住宅の壁の下地(間柱)は多くの場合、約30〜45cm間隔で配置されているため、20cm間隔で探せば必ず見つかります
- 植木鉢の配置:観葉植物を20cm間隔で配置すると、風通しが良く、見た目にもバランスの取れた配置になります
裁縫と手芸
裁縫や手芸においても、20cmは重要な基準となります。
【活用術】
- 基本的な裾上げ:ズボンの裾上げは通常5〜10cmですが、20cmを基準にすると、大幅なリフォームの目安になります
- 編み物のゲージ:編み物の密度を測る際、20cm四方のゲージを取ると、出来上がりのサイズが計算しやすくなります
- パッチワークのサイズ:20cm四方のパッチを基本単位にすると、キルトやクッションカバーなど様々なサイズの作品が作りやすくなります
ガーデニング
庭づくりでは、植物の間隔や深さを決める際に20cmの感覚が役立ちます。
【活用術】
- 球根の植え付け深さ:多くの花の球根は、その大きさの2〜3倍の深さ(約20cm)に植えると育ちやすくなります
- 草花の間隔:小〜中型の草花を植える際、20cm間隔で植えると成長しても混み合わず、見栄えも良くなります
- 土づくり:庭の土壌改良をする際、約20cmの深さまで耕すと、多くの草花や野菜が育ちやすい環境が整います
【実践テクニック:20cmの活用幅を広げる】
- 普段の生活の中で「ここは20cmあるといいな」と思う場面をメモする
- 20cmという長さがちょうどいい場面を探す習慣をつける
- 20cmの感覚を磨くことで、日常生活での「目測」の精度を上げる
教育と20cm
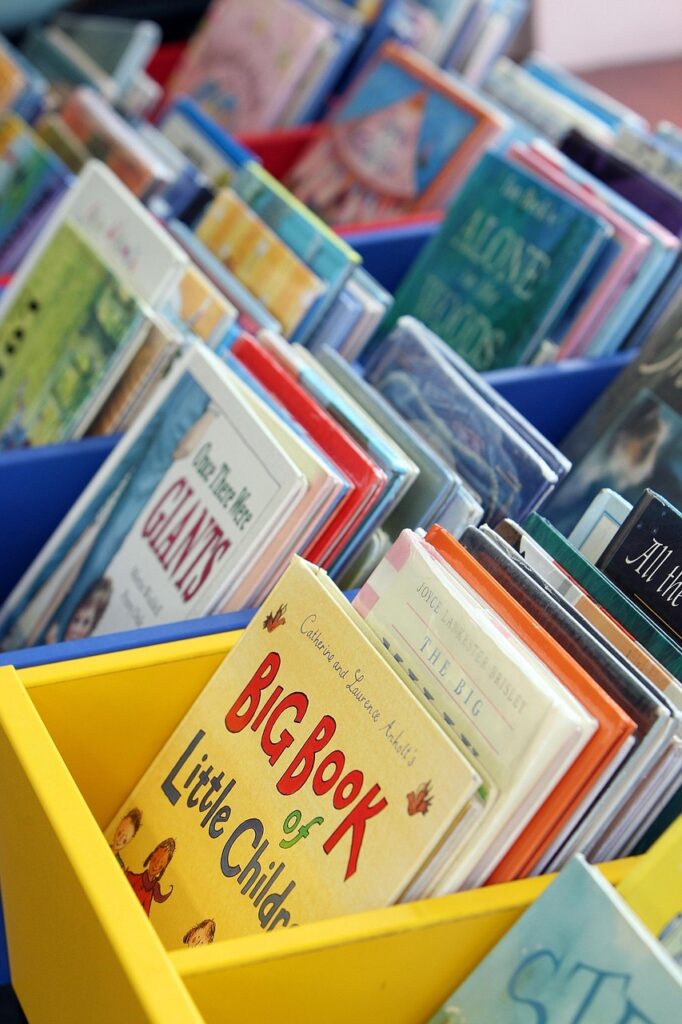
子どもたちに単位の概念を教える上で、20cmは非常に分かりやすい基準となります。
教育現場での活用方法を紹介します。
子どもに教える方法
子どもが理解しやすい20cmの例を挙げ、楽しく学べる工夫をします。
【教育術】
- 「お気に入りのおもちゃと同じくらい」など、子どもにとって身近なものと比較する
- 子どもの手の広がりがどれくらいで20cmになるか、一緒に測ってみる
- 20cmの紐や棒を作り、「20cmメジャー」として使えるようにする
遊びながら学ぶ
遊びの中で自然と20cmの感覚を養う方法を取り入れます。
【遊びのアイデア】
- 「20cmジャンプ」:20cm離れた場所に目印を置き、ジャンプの距離感を養う
- 「20cmドロー」:目を閉じて20cmの線を描く競争をする
- 「20cmハント」:部屋の中から20cmのものを探す宝探しゲーム
学習教材への応用
学校の授業や家庭学習で20cmを活用した教材を作ります。
【教材アイデア】
- 20cmを基準にした様々な単位変換カード(20cm = 2dm = 約8インチなど)
- 20cm定規を使った図形描画の練習帳
- 20cmの身近な例を集めた絵本やカード
観察力を育てる
20cmという基準を使って観察力を高める活動を取り入れます。
【観察アイデア】
- 自然の中で「20cmのもの」を探す観察日記をつける
- 成長記録として植物の20cm到達を記録する
- 20cmの枠を使って風景を切り取る写真撮影ゲーム
【実践テクニック:子どもと一緒に20cmを学ぶ】
- 子どもが興味を持つテーマ(恐竜、乗り物など)と20cmを関連付ける
- 日常の会話の中で「これは20cmくらいだね」と意識付けをする
- 子どもの成長記録を20cm単位で取り、変化を実感できるようにする
まとめ:身近な20cmの価値を再確認
20cmという一見何の変哲もない長さも、日常生活の中で見つめ直してみると、様々な場面で活躍していることがわかります。
日常にある20cmの価値再確認
- 測定道具がなくても、身の回りのものや自分の体を使って20cmを測れることが分かりました
- 料理、DIY、裁縫、ガーデニングなど、様々な生活シーンで20cmという単位が基準として使えます
- 子どもの教育において、具体的な長さの概念を教えるのに最適な長さです
5つの記憶法のおさらい
- 比較記憶法:身近なものとの比較で20cmを覚える
- 指標作成法:自分の体を使って20cmを測れるようにする
- 視覚化技術:20cmの長さを視覚的にイメージする
- 実践トレーニング:日常的に20cmを意識して使う
- 環境設定法:生活環境に20cmの目印を設置する
活用術の要点
- 日常生活の中で、20cmの感覚を常に意識する
- 目測の精度を上げることで、測定器具がなくても適切な判断ができるようになる
- 子どもと一緒に20cmについて学ぶことで、単位の概念を楽しく教えられる
「20cm」は私たちの身の回りに無数に存在していますが、それを意識して捉えることで、新たな視点から日常生活を見つめ直すことができます。
この記事で紹介した50の例と5つの覚え方を実践して、あなたも「20cmの達人」になってみませんか?
関連記事